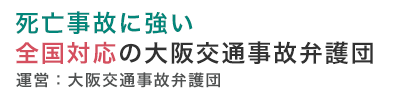コラム
死亡慰謝料の増額(2)
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、本年最初のコラムは、前回に引き続き「死亡慰謝料の増額」をテーマに取り上げます。今回は、「一家の支柱」となる方が死亡されたケースについて、いくつかの事例を紹介したいと思います。
なお、被害者が「一家の支柱」である場合の死亡慰謝料の標準額は一般に2800万円とされています(前回のコラム「死亡慰謝料の増額(1)」も併せてご覧下さい。)。
① 東京地裁平成16年2月25日判決・自保ジ1556号13頁
54歳の男性が被害者となった死亡事故で、加害者が酒酔い運転で車両を対向車線に進入させたことにより事故が生じたこと、加害者が事故後に救助活動を一切しなかったこと、刑事事件の捜査段階において被害者がセンターラインを先にオーバーしてきたなどの虚偽の供述を行ったことなどを考慮し、本人分として2600万円、妻と母についてそれぞれ500万円の合計3600万円の慰謝料が認められました。
② 大阪地裁平成25年3月25日判決・自保ジ1907号57頁
30歳・会社員の男性が被害者となった死亡事故で、加害者が無免許の飲酒運転であった上、事故現場から逃走し、被害者を約2.9㎞にわたり故意に引きずり死亡させたという殺人罪にも該当する極めて悪質かつ残酷なものであること、引きずられながら絶命した被害者の苦痛苦悶は筆舌に尽くしがたいこと、30歳にして妻と子を残して突然命を奪われた被害者の無念さ等を考慮し、本人分として3500万円、妻と子についてそれぞれ250万円ずつの合計4000万円の慰謝料が認められました。
③ 東京地裁平成25年12月17日判決・交民46巻6号1592頁
33歳・会社員の男性が被害者となった死亡事故で、加害者が、車上荒らしが発覚してパトカーの追跡から逃れようとして反対車線を時速約80㎞で走行したこと、事故後に被害者を救護しなかったこと、被害者が結婚式を挙げたばかりであったこと等を考慮し、本人分として3200万円、妻分として400万円、父母についてそれぞれ250万円の合計4100万円の慰謝料が認められました。
次回は、「母親・配偶者」の方が死亡されたケースについて具体的な事例をご紹介いたします。
弁護士 柳田 清史
過失割合
さて、今年も残すところあとわずかとなりました。今年最後のコラムは、過失割合をテーマにしたいと思います。
交通事故の裁判実務では、日々多くの事故が発生しているため、公平性の観点などから、判例タイムズ社から出版されている、別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」という書籍により、事故の類型ごとに過失割合(過失相殺率)が基準化されています。死亡事故においても、保険会社から上記判例タイムズに基づいて、過失相殺の主張がなされるケースがしばしばあります。
もっとも、ここで重要なことは、上記判例タイムズに記載された基本的な過失割合(過失相殺率)は典型的な事案を前提としたものにすぎませんので、必ずしも当該事案において、保険会社が主張している過失割合が妥当しないケースがあるということです。
このようなケースでは、証拠に基づいて、説得的に適正な過失割合を主張する必要があり、特に、死亡事故の場合には、被害者ご本人の供述がないため、遺族の方ご自身で適正な過失割合を主張していくことは困難を伴うものと思われますので、過失割合に納得がいかないという方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士 疋田 優
賠償額から控除されるものは何?
交通事故により被害者が死亡した場合でも、被害者の遺族が、被害者の死亡を原因として何らかの給付を受けている場合、その給付等の額が賠償額から控除されることがあります。これは、いわゆる損益相殺と言われるもののほか、その他の根拠でも賠償額の算定において控除されるものがあります。
今回は、そのような項目のうち、裁判例上、一般に賠償額から控除されるものと控除されないものについて整理したいと思います。
1 賠償額から控除されるもの
①加害者側(保険会社を含む)からの弁済
②自賠法に基づく給付
・自賠責保険会社からの損害賠償額の支払い
・政府補償事業による損害の填補額の支払い
③各種社会保険給付
・労災保険法による遺族年金、遺族一時金、遺族年金前払一時金(詳細は柳田弁護士のコラム「死亡事故と労災保険⑵」をご
参照ください)
・国家公務員災害補償法による遺族補償金
・国民年金法による遺族基礎年金
・厚生年金保険法による遺族厚生年金
・国家(地方)公務員等共済組合法による遺族年金
・国家公務員等退職手当法による退職手当
・恩給法による扶助料
2 賠償額から控除されないもの
①見舞金等
②労災保険法による特別支給等
・遺族特別年金、遺族特別一時金、遺族特別支給金など
③定額保険等
・搭乗者傷害保険金、自損事故保険金、その他の各種定額の傷害保険金
・生命保険金
以上に挙げたものについては、それぞれに最高裁判決があり、賠償額から控除される根拠・控除されない根拠にはさまざまな理論的な問題があります。また、事案や金額によっては結論が異なることもあり得ます。
これらの詳細については、またコラムにてご紹介したいと思いますが、どのような給付が賠償額から控除されてしまうのかについては、難しい問題がありますので、まずは弁護士にご相談をいただくことをお勧めします。
弁護士 田 保 雄 三
交通事故の相手方が無保険だったらどうする?
交通事故に遭ったものの、加害者が保険に未加入の場合があります。
自動車保険には、①任意保険と②自賠責保険がありますが、今回の私のコラムでは交通事故の相手方が前者の任意保険に未加入だった場合の対応のうち、特に治療費、慰謝料等の人身損害賠償の問題を中心に解説します。
損害保険料率算出機構が実施した調査によると、任意保険の対人対物賠償責任保険に加入している車両の割合は約70%であり、世の中の約3割の車両は任意保険未加入というデータがあるようです(もちろんまったく使用されていない車両もあるため、実際に公道を走っている任意保険未加入の車両の割合はもっと少ないと推測されます)。交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、保険会社の「示談代行サービス」が使えません。特に、交通事故でけがをした被害者としては、次のような対応が考えられます。
(1)加害者と直接交渉する
まず、交通事故の加害者に対し、直接治療費や慰謝料を支払うよう交渉するのが原則です。しかしながら、相手方被害者と直接交渉する場合、そもそも連絡がつかない、慰謝料の計算の方法がわからない、加害者が約束を守らないなど、様々な問題が予想されます。
(2)被害者自身が加入する任意保険の特約を利用する
相手方加害者が治療費や慰謝料等の支払いに応じない場合、被害者自身が加入する任意保険を利用する方法があります。例えば、人身傷害保険に加入していると、被害者自身が加入する保険会社から治療費、交通費、慰謝料等の保険金の支払いを受けることができます。また、搭乗者傷害保険も同様に、被害者自身が加入保険会社から保険金が支払われます。もっとも、これらの保険金は損害の全額を補填するものではなく、不足する部分については、加害者本人に直接請求するほかありません。
(3)加害者の自賠責保険に被害者請求する
被害者自身が加入する保険から保険金が支払われない場合、被害者としては、加害者の自賠責保険に対し、「被害者請求」という方法により治療費、慰謝料等の保険金することができます。また、事故の後遺症が残った場合にも、被害者請求により後遺障害の等級認定を受ければ、保険金を受領することが可能です。もっとも、被害者請求の手続には多くの書類を準備する必要があり、非常に煩雑です。また、自賠責保険から支払われる保険金は、損害の全額を補填するものではなく、不足する部分については、加害者本人に直接請求するほかありません。
以上に加えて、車両の修理費などの物損賠償の問題も考えられます(この点は次回以降のコラムで取り上げる予定です)。このように交通事故の相手方が任意保険に未加入の場合、けがをした被害者は、対応に大変な苦労をされることが予想されます。相手方が任意保険に未加入であることが判明した時点で、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士 藏 田 貴 之
「個人事業主の方が死亡事故の被害者となった場合の逸失利益の算定について」
さて、前回は、会社役員の方が死亡事故の被害者になった場合の死亡逸失利益について取り上げましたが、今回は、個人事業主の方が死亡事故の被害者となった場合の死亡逸失利益の基礎収入の算定をテーマにしてご紹介したいと思います。
まず、死亡事故以外の場合又は死亡事故のケースでも事故で傷害を負った後に一定の期間経過後にお亡くなりになったケースでは、症状固定時までは休業損害として請求することになります。この場合の基礎収入は、申告所得額の金額に固定経費(例えば、公租公課、損害保険料、減価償却費等の事業継続のためにやむを得ない出捐をいいます。)を加算して請求することができます。
他方、後遺障害逸失利益や死亡逸失利益の基礎収入の算定においては、通常、固定費を加算する取り扱いはできないと考えられています。これは、休業損害の基礎収入額の算定において申告所得額に固定費を加算できるのは、固定費が休業期間中も将来の事業継続のために従前どおり支払を継続しなければならず、いわば休業期間中に無駄な支出を余儀なくされたと評価できる経費であると考えられているからです。そのため、このような評価ができない後遺障害逸失利益や死亡逸失利益の基礎収入の算定においては、固定費を基礎収入に算定できないと考えられています。
弁護士 疋田 優
死亡慰謝料の増額(1)
死亡事故においては、事故態様の悪質性などから慰謝料の増額が認められる場合があります。今回は、死亡事故において慰謝料の増額が認められる場合について、取り上げたいと思います。
まず、死亡慰謝料については、亡くなられた方の立場に応じて、以下の基準に従って算定されるのが一般的です(「死亡事故の慰謝料相場と支払基準」もご参照下さい。)。これらの額には、原則的に近親者固有の慰謝料も含まれます(本サイトのコラム「死亡事故被害者の兄弟は固有の慰謝料を請求できる??」、「遺族固有の慰謝料請求権を高額化する事情について」等もご参照下さい。)。
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他 2000万円~2500万円
もっとも、①酒酔い運転、無免許運転、ひき逃げ、大幅なスピード違反による事故など、事故態様が悪質な場合や、②謝罪がない、事故について虚偽の説明を行うなど、事故後の加害者側が著しく不誠実な対応を行っている場合には、上記の基準を超えて慰謝料の増額が認められることがあります。
例えば、東京地裁平成15年3月27日判決では、一家の支柱であった被害者の死亡事故において、加害者が飲酒酩酊状態で高速道を逆走するという常軌を逸した運転により事故を発生させたこと、加害者が事故後直ちに遺族らのもとへ謝罪に赴かないなど謝罪意思の表明の在り方において配慮に欠けた面があったこと等を理由に、3600万円の慰謝料が認められています。
また、近親者の固有慰謝料についても別途増額が認められた事例として、東京地裁平成24年3月27日判決では、両親を死亡事故で亡くした子ら4名が加害者に対し損害賠償を請求した事案で、加害者が長時間にわたる飲酒により高度酩酊状態となり、高速道でセンターラインオーバーにより対面被害車両に正面衝突した事故であること、加害車両の同乗者が運転者の刑事裁判では運転者の関与を認めたのに自身の刑事裁判では不合理な弁解に終始したこと等を理由に、両親の本人分慰謝料(一家の支柱)として各3200万円、子4人について各400万円の合計8000万円の慰謝料を認めています。
これらの事案は、上記の標準的な慰謝料基準と比較すれば、大幅な慰謝料の増額が認められた事例といえます。遺族の方にとって、悪質な交通事故によって大切なご家族を失われた悲しみが消えることはありませんが、加害者に対して民事上も悪質な死亡事故について然るべき責任を追及し、その精神的苦痛が慰謝料の増額という形で裁判所に認められることは、当弁護団としても非常に意味があることだと考えています。
悪質な死亡事故でご家族を失った方、加害者の不誠実な対応にお悩みの方は、是非一度当サイトへお問い合わせ下さい。
弁護士 柳田 清史
葬儀費用はなぜ150万?
交通事故により被害者が死亡した場合、裁判実務では、葬儀関係費として原則150万円が損害賠償として認められています(当サイト内の「死亡事故の損害賠償の種類」参照)。
ただし、実際に支出した額が、150万円を下回る場合、実際に支出した額しか損害として認められません。
また逆に、実際に支出した額が150万円を上回っていても、150万円以上は損害として認められないのが一般的です。
葬儀費用は人によっても異なるのが通常ですし、150万円以上かかるケースも多いと考えられます。
なぜこのように「150万円」という基準で運用されているのでしょうか。
理由として挙げられるのは以下の点です。
① 個々の被害者について、社会通念から見て必要かつ相当とされる葬儀費用等を客観的な数値として認定することは容易でない。
② 葬儀の規模や方法は、実際には被害者及び遺族の社会的地位等によって異なるところ、そのような社会的地位等による格差を全面的に容認することになれば、同じ交通事故の被害者であるにもかかわらず、葬儀費用等として賠償が認められる金額に差異が生じることとなり、不公平を生じさせるおそれがある。
③ 葬儀費用等は、交通事故による死亡がなかったとしてもいずれ支出を避けがたい性格のものであり、現実の損失としては、支出時期が早まったことによる利息分の損害に限られると考えることができる。
④ 実際に葬儀等においては香典収入があるため、遺族が最終的に負担することとなる金額は現在の裁判実務で基準とされている金額に近くなると考えられる。
このようにしてみると、なぜ150万なのかについては、だれが見ても納得できる理由付けがされているとは必ずしも言えない気がします。
これらの根拠が妥当と言えるかどうかは、もちろん議論の余地がありますし、実際、裁判例においても、150万円に限られないと主張して葬儀費用代を争っていくケースもあります。
葬儀費用に限らず、一律の基準で運用されているものであっても、果たして妥当かどうか、という点は、一度弁護士にご相談されてみることをお勧めします。
弁護士 田 保 雄 三
運転代行を頼んだときの事故の責任は誰が負う?②
自動車に乗って出かけて、お酒を飲んだ帰り道、「自動車運転代行」を利用する方も多いかと思います(間違っても飲酒運転は、絶対に避けてください)。今回の私のコラムでは、前回に引き続き、「運転代行を利用中、利用者自身がけがを負わされた場合に誰が事故の賠償責任を負うのか」について、解説します。
1 賠償責任の所在
結論から言うと、運転代行を利用中、利用者自身がけがを負わされた場合、利用者は運転代行業者に対して、損害賠償を請求できます。まず、利用者と運転代行業者との間には、利用者の自動車を運転して利用者と自動車を安全に運ぶサービスを提供し、利用者は提供されるサービスに対して料金を支払うという契約関係があります。利用者は、運転代行業者に対し、契約上の義務違反として損害賠償を請求できます。また、運転代行業者は、利用者との関係では、自動車損害賠償保障法第3条の運行供用者責任を負うと解釈されています(最高裁判所平成9年10月31日判決)。
2 賠償保険の利用
代行業者に十分な支払能力がない場合、利用者の損害を賠償してくれる保険の存在が重要となります。まず、運転代行業者は、法令に基づき、対人賠償8000万円、対物賠償200万円以上の自動車保険または共済に加入する義務があります。したがって、多くの場合、運転代行業者が加入する保険が利用者の損害を賠償してくれます。また、運転代行業者の中には保険に未加入の業者もあり、利用した業者が保険未加入だった場合には、利用者自身の自動車の自賠責保険が利用できます。したがって、運転代行業者が保険未加入の場合でも、自賠責保険の補償の範囲内であれば、賠償を受けることができます。
これまで2回のコラムでは、運転代行を利用した場合の損害賠償の問題を取り上げましたが、運転代行業者を利用中の交通事故については、賠償の責任の所在が複雑です。適正な賠償が受けられるか不安に思われる方は、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 藏 田 貴 之
個人事業主の逸失利益はどうやって算定する??
前回に引き続き、今回は、個人事業主・事業所得者(以下、単に「事業所得者」といいます。)の死亡逸失利益を取り上げたいと思います。
事業所得者の場合も、死亡逸失利益の算定方法自体は一般的な場合と同様です(「死亡事故の損害賠償の種類」(2)消極損害もご参照下さい。)が、基礎収入の算定については、原則として事故の前年度の確定申告所得額(青色申告の場合は、青色申告控除前の所得額)によって認定されます。もっとも、ケースによっては、申告をされていない場合や、申告額が実際の所得よりも低額である場合などがありますが、このような場合に、逸失利益はどのように算定されるのでしょうか。
① 無申告の場合
この場合でも、実際の収入状況が立証できれば、現実の収入が基礎収入として認められますが、その立証が難しい場合は少なくありません。そのような場合でも、事業の実態があり、相当の収入があったと認められる場合には、賃金センサスなどが参考にされて基礎収入が認められる場合があります。
② 申告外所得がある場合
この場合も実際に申告外所得の存在が立証されれば、基礎収入として認められますが、税務署へ申告している所得と矛盾する所得の存在を主張することとなるため、その認定は非常に厳格に行われます。申告をしている収入や諸経費と実際のそれらが異なることについて、会計帳簿等の信用性の高い証拠によって、高度な立証が求められるため、実際に認定を受けることも難しい場合が多いと言えます。
もっとも、極端に申告所得が少なかったり、赤字申告をしている場合で、その所得では明らかに生活水準が維持できないと考えられる場合や、開業・転業後間もない時期である場合、過去の収益が赤字であっても将来給与所得者への転職が予想されるなど相当の収入が得られる蓋然性が認められる場合などは、賃金センサス等を参考に一定の基礎収入が認められる場合があります。
以上のとおり、事業所得者の逸失利益についても、人により様々な事情があることから、どのように基礎収入が認定されるかによって、賠償額が大きく変わってくる可能性があります。また、事業収益に家族の寄与がある場合や、職種によっては異なる特別の事情を考慮しなければならない場合もあります。
当弁護団では、無料法律相談も実施しておりますので、是非お気軽にご活用下さい。
弁護士 柳田 清史
会社役員の方が死亡事故の被害者となった場合の逸失利益の算定について
さて、今回は、会社役員の方が死亡事故の被害者となった場合の死亡逸失利益の算定について、被害者の方が会社役員である場合によく問題となる基礎収入の算定をテーマにしてご紹介したいと思います。
まず、死亡事故以外のケースにおいて、会社役員の逸失利益に関する基礎収入は、労務対価部分に限るものされていることに異論はありません。そして、会社役員の基礎収入には実質的な利益配当部分が含まれていることがままあることから、会社役員である被害者の方が受領していた役員報酬のうち労務対価部分の額に関して争いになるケースが多くあります。なお、その役員報酬中の労務対価部分は具体的にどのように判断されるのかという点は次回に述べたいと思います。
他方で、死亡事故のケースでは、役員の地位も失うため、死亡事故以外のケースと異なり、利益配当部分も含めて役員報酬全体を基礎として逸失利益を算定すべきではないかという議論があります。もっとも、裁判例では、死亡事故事案で基礎収入を労務対価部分に限定するケースや、役員報酬全額を基礎収入と判断している事案についても、その理由付けとして労務対価部分に言及しているケースも多いため、必ずしも死亡事故のケースで、利益配当部分を含めて役員報酬全体を基礎として逸失利益を算定しているとは言い難い状況であると思われます。
このように、会社役員の方が死亡事故の被害者となったケースでは、大変悩ましい問題が生じ得ますので、お悩みの方は無料法律相談等をご活用のうえで弁護士に一度相談されることをおすすめします。
弁護士 疋田 優
« Older Entries Newer Entries »